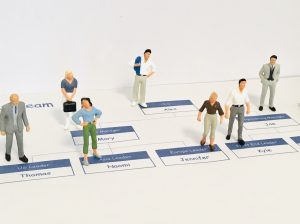リレーBLOG第14弾「お茶と着物」
11期秋入学の張と申します。今回は同期の菅谷さんから執筆の機会を頂きました。女性目線で、今までにない新鮮な内容でというご要望を頂戴いたしましたので、普段は外資のカーボンブラックメーカーで技術営業や、開発の業務をしておりますが、今回はここ数年の自身の関心事である、茶道にまつわるお話をさせていただきます。
2年前、茶道を習おうと思い立ち、表千家、裏千家どちらにしようかと一瞬迷いましたが、平日のお稽古は受けられず、時間と場所の合った表千家を選ぶことにしました。

お稽古の内容は、お道具を運んでお茶を一服立てる通し稽古です。初心者にはかなり厳しく、上手な人のやり方をひたすら覚えるしかありません。初日で心と足が折れそうに。この先続けられるか不安になり、他の生徒さんにアドバイスを乞うことにしました。
アドバイスは YouTubeを見て、一通り勉強してからお稽古に挑むこと。
茶道の所作が動画に?!とかなり驚きましたが、検索してみると動画がずらり。時代がいつの間にか変わっていたようです。YouTubeを見て一通りの手順を覚えた後、お稽古で実践。お稽古でできなかった部分を何度も見返し可能な動画を利用して復習します。けれど動画だけだと場の雰囲気がわからず、やっぱりお稽古の必要なことに気付きます。この繰り返しが実に効率的で、良いことに気づきました。

そうこうしている間に、1年が経ち発表会を兼ねたお茶会。ということは、そう、着物です。
幸い着付けを数十年前に習っていたので、着物、帯等も一式揃い、なんとなくは自分で着ることもできましたが、やっぱり細々とした所が思い出せず。
そこで、お稽古で学んだようにYouTubeを検索してみることに。すると着付けの動画がわんさか。私が着物の着付けを習っていた頃は、着付けの方法を動画に収めること自体がご法度に近かったような気がします。何かを覚える時は、見て、後でメモに書いて覚えるものであり、写真や動画は努力不足といったような雰囲気、昭和の方はわかって頂けるのではないかと思います。そう思うとYouTubeに着物の着付けや茶道の作法を最初にアップロードした人は相当ひどい批判を受けたのではないでしょうか。世代によっては受け入れられないような気がします。でも、多くの人が待ち望んでいたのではないでしょうか。

数十年前に揃えた着物と帯を着て、いざお茶会へ。あれ?なんだか私を見て、なんとも言えない表情をする人達が。きっと何かしでかしている感じです。
そういえば、一点気になることが。それはお稽古の時耳にした、着物の格。まったく調べずに来てしまいました。帰宅後、さっそくYouTubeで着物の格を調べました。出てくる出てくる、値段ではない着物の格情報。振袖、留袖、訪問着、小紋くらいは耳にしていましたが、色無地の格?しかもそこに’紋‘の数、種類による格の上り下がり。。。蒼ざめました。
着付けを習った時に一通り習った気もしますが、すっかり記憶から抜け落ち、記憶に残ったのは買った着物と帯の値段だけ。着物の格は、帯の格、帯締め、帯揚げの格にも繋がっていて、知れば知るほど身動きが取れなくなりそうな感じです。全て正解を選ぶ事をとりあえず諦めました。
調べた結果、着物を一式買い替えないといけないことに気づきました。もしかしてと思いネットの力を借りることに。着物の中古をネットで探しました。すると、かなり質のいい着物と帯が考えられない値段で売り出されています。数十年前に買って以来数回しか着ていない着物と帯。同じ産地のものが、10分の1から、100分の1の値段で手に入ります。そして選べるのです。信じられませんでした。
夢のようではありますが、着物の市場はどうなっているのでしょうか、着る人は増えているのでしょうか、伝統工芸は今後も続いていけるのでしょうか、いろんな思いが巡ります。

この文章を読んでいただいた皆様、ぜひ今一度着物を着る機会について思いを巡らせて頂ければ嬉しく思います。ネットサーフィンでかなりの着物の種類を眺められ、お手頃価格から着物を購入する事も出来るので、気がるに着付けに挑戦するのもおすすめです。
<加藤宗恭(そうきょう)先生からコメントが届いています。宗恭って誰?と思った人は→>
茶道のお点前から茶会時の着物の格に関する説明まで、かつては指導者や経験者とのつながりがなければ得られなかった情報が、今では簡単に手に入る時代になりました。張さんのエッセイを拝読し、IT技術の進歩によって伝統文化への敷居がぐっと低くなったことを改めて実感しました。
一方で、同じ技術の進歩によって国や文化の物理的な境界が薄れつつある中、その国独自の伝統文化や芸能への関心が高まっているのは興味深い現象だと感じています。特に、外国人の茶道(Chado)熱には目を見張るものがありますね。
張さんがおっしゃるように、最近では質の良い着物や帯だけでなく、茶碗や茶杓、棗などの茶道具も中古市場で比較的安価に入手できるようになりました。
過去には限られた人々のみが親しんできたこの文化に、誰もが簡単にアクセスできるようになった今、日本に住む私たちこそがその魅力を改めて味わい、受け継いでいく時なのかもしれません。